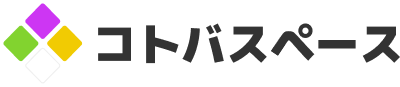ことわざは、自然界から教えを学んで教訓にしたものも数多くあります。その中で「どうぶつ」の名前が入っているものをピックアップしてみました。人の暮らしとどうぶつの関わりは、切っても切れないものがありますね。
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 足元から鳥が立つ | 突然身近なところから思いがけないことが起こる。急に思いつきで物事を始めること。 |
| 犬も歩けば棒に当たる | 何もせずにじっとしているより、何でもいいから行動してみれば、思わぬ幸運にめぐり合うかもしれないということ。また逆に災難にあう可能性もあるという意味もある。 |
| 牛に引かれて善光寺参り | 自分の意志ではなく、他から誘われて思いがけないよくことに巡りあうこと。 |
| 鵜の真似をする烏 | 自分の才能のほどを考えずに、見よう見まねで人の真似をすると必ず失敗するということ。 |
| 鵜の目鷹の目 | 熱心にものを探す様子 |
| 馬の耳に念仏 | いくら言い聞かせても、効き目がないこと。ありがたみがわからないこと。 |
| 飼い犬に手を噛まれる | 世話をしてあげた人、信用している人に裏切られること。 |
| 河童の川流れ | どんな名人でも、油断をすると失敗してしまうこと。 |
| カラスの行水 | 入浴・お風呂に入る時間が極めて短いこと。お風呂があっさりしていること。 |
| 雉も鳴かずば撃たれまい | いわなくてもいいことをしゃべると災いを招くということ。時には大人しくしている方がいいということ。 |
| 犬猿の仲 | 仲の悪い間柄。修復できない仲の悪さ。 |
| 塞翁が馬 | どんな災いも幸せのもとになるかもしれないし、どんな幸せも災いのもとになるかもしれない。人が生きていくうえで、何が幸せを招き、何が不幸を招くかは分からないということ。 |
| 猿も木から落ちる | どんな上手な人にも、やりそこないということはある。その道に長けた人も、時には失敗があるということ。 |
| 雀百まで踊り忘れず | 幼いころに身につけたこと・習慣は、年をとってもなかなか変わることができないということ。 |
| 立つ鳥跡を濁さず | 立ち去るときは今までいたところを綺麗にしてから出るべきだということ。立ち去ったあとに揉め事などがないように始末しておくこと。 |
| 角を矯めて牛を殺す | 欠点を直そうとして、厳しい手段をとったため、かえって全体をダメにしてしまうこと。 |
| 鶴の一声 | 大勢の人たちが議論してまとまらなかったことが、偉い人の一言でそのまますぐに決まってしまうこと。つまらぬものの多くの声よりも優れた人の一声のほうが価値が高いという意味。 |
| 鳶が鷹を生む | 平凡な親から優れた子が生まれること。 |
| 鳶に油揚げをさらわれる | 不意に横から手柄や利益、大事なものを横取りされること。 |
| 取らぬ狸の皮算用 | 当てにならない収穫、収入を見越してあてにすること。まだに手に入れていないうちからあてにして、儲けを計算したり、あれこれ計画を立てたりすること。 |
| 虎の威を借る狐 | 他人の権威をかさにして、自分を大きなものとみせること。威張る人。 |
| 二兎を追う者は一兎をも得ず | 一度に二つのものを得ようとすると、どちらも得ることができないという戒め。 |
| 猫に鰹節 | 相手の好物をそばにおいて置くのは取られるのを待っているようなもの。間違いを起こしやすい状態になっているということ。 |
| 猫に小判 | どんなに値打ちのあるものでも、その値打ちの分からない人には、何の役にも立たないこと。値打ちがわからないこと。 |
| 猫の首に鈴をつける | とても危険なことに挑むという時や、難題にあれこれと話し合って出された考えでも誰も実行できないということ。 |
| 猫の額 | 面積が極めて狭い場所のこと。 |
| 能ある鷹は爪隠す | 本当に実力のある人は、それをやたら見せびらかしたりしないこと。 |
| 豚に真珠 | どんなに値打ちのあるものでも、その値打ちの分からない人には、何の役にも立たないこと。値打ちがわからないこと。 |